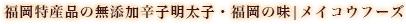明太子の歴史、知ってる?ちょこっと雑学コラム
白いご飯やおにぎり、パスタにと大活躍の明太子。ピリ辛でプチプチとした食感がたまらない、日本の味としてすっかりおなじみですよね。でも、この明太子がどのようにして生まれたのか、その歴史をご存知でしょうか?今日はちょこっとだけ、明太子の歴史をご紹介したいと思います。
実は、明太子のルーツは日本ではなく、朝鮮半島にあると言われています。「ミョンランジョッ(明卵漬)」と呼ばれるスケトウダラの卵の塩漬けが、その原型だとされています。唐辛子を使った漬け込み方もあったようですが、日本の「辛子明太子」とは少し異なっていたようです。
では、私たちがよく知る「辛子明太子」はどこで誕生したのでしょう?それは、戦後の日本の博多でした。引き揚げてきた「ふくや」の創業者である川原俊夫氏が、故郷である釜山で食べた「明卵漬」の味を忘れられず、「日本人の味覚に合うように」と試行錯誤を重ねて作り上げたのが、今の辛子明太子の始まりだと言われています。
辛さや塩加減、漬け込み液の配合など、長い時間をかけて研究が重ねられ、独特の旨味と辛味を持つ「辛子明太子」が完成しました。博多の港町という土地柄や、食に対する探求心も相まって、辛子明太子は徐々に博多の名物として定着していきました。
何気なく食べている明太子にも、海を越え、時代を超えた物語があると思うと、いつもの一口が少し違って感じられるかもしれませんね。ぜひ、メイコウフーズの明太子で、博多の味の歴史と私たちのこだわりを感じていただけたら嬉しいです。